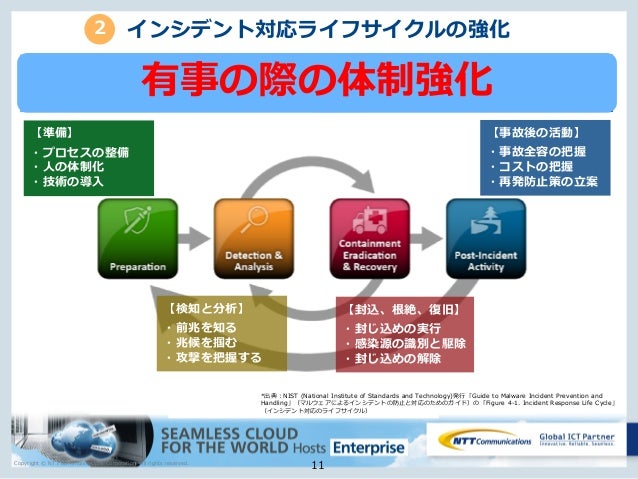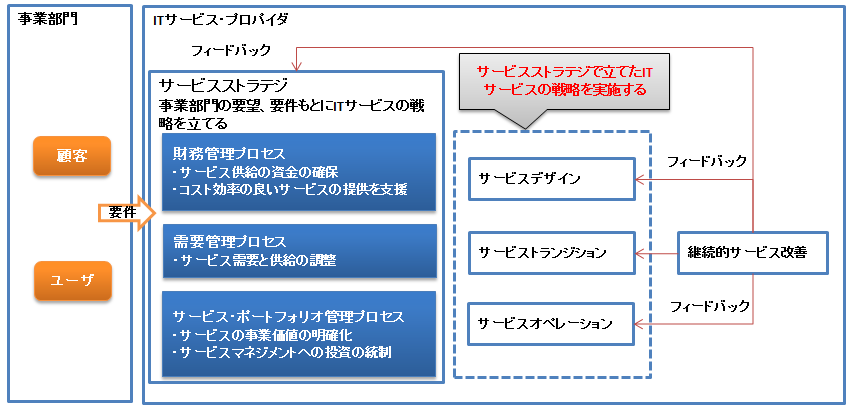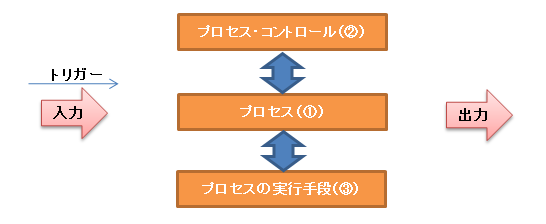□サービスオペレーション
問い合わせの受付や、障害に対処するなどの活動で合意済みのサービスレベルでITサービスを提供できるようにする。
サービスオペレーションプロセスの概要
・イベント管理
ITサービスの提供に必要なサーバ、アプリケーションなどから通知されるすべてのイベントを監視し、異常状態を通知するイベントが発生した場合にインシデント管理プロセスにエスカレーションする
・インシデント管理
できるだけ早くインシデントを取り除くことを目的とする活動を行う。その為、インシデント管理プロセスでは根本原因の調査や解決などは行わない。
・問題管理
問題の根本原因の特定、除去を目的とする活動を行う。原因を特定できると変更要求を変更管理プロセスに依頼する。
・要求実現
ユーザから要求されるリスクが少なく低コストで発生頻度が多い作業をあらかじめ合意された手順に従って処理する。
・アクセス管理
許可されたユーザにITサービスを使用する権限を付与、付与された権限が適切に使用されているか確認する。
サービスオペレーションの機能の概要
・サービスデスク
ITサービスプロバイダとユーザ間の接点となる組織。インシデント、サービス要求、標準的な変更を受付、処理する。
・IT運用管理
ITインフラストラクチャを継続的に管理、保守し合意されたレベルでITサービスを提供するために必要になる
・技術管理
ITインフラストラクチャを継続的に管理、保守し合意されたレベルでITサービスを提供するために必要な技術力やリソースを提供する
・アプリケーション管理
運用中のアプリケーションの管理とサポートを担当する。
サービスオペレーションにおけるコミュニケーション
コミュニケーションの要件
・運用に関する日常的なコミュニケーション
→サービスオペレーションの定期的な活動を調整する
・シフト間のコミュニケーション
→シフト制でのシフト間の引き継ぎ
・パフォーマンス報告
→ITサービスのパフォーマンスなどを報告
・プロジェクトにおけるコミュニケーション
→プロジェクトの目標や進捗の確認を行う
・変更に関するコミュニケーション
→変更管理プロセス、リリース管理、展開管理プロセスを支援する
・例外に関するコミュニケーション
→インシデントや予想外の活動やパフォーマンスの報告をする
・緊急事態に関するコミュニケーション
→インシデントのインパクトや重大度を調査して確認し実際に緊急事態であることを確認する
・グローバルなコミュニケーション
→複数の国に跨ってサービスを提供する場合、様々な国のユーザ・顧客・ITスタッフ間でグローバルにコミュニケーションをとることで運用リスクを下げる
・ユーザ及び顧客とのコミュニケーション
→顧客またはユーザの要件を満たすために顧客とコミュニケーションをとる
□イベント管理
イベント:CPU使用率が許容できる稼働率を超えている、バッチジョブが異常終了したといったITサービスの管理にとって重要な状態の変更のこと
情報・警告・例外に分類され、通常はイベント管理ツールを用いて管理されている。
□インシデント管理
ITサービスに対する計画外の中断や品質の低下を管理する。
重要なことはインシデントを漏れなく管理すること、解決までのステータスを追跡すること。
インシデント:ITサービスの計画外の中断や品質低下のこと
インシデントが報告される経路
・サービスデスク経由
・イベント管理プロセス経由
・技術スタッフ経由
インシデントモデル
特定の種類の再発するインシデントの処理手順を定義しておくこと
定義する項目
・インシデント処理手順
・処理手順の優先度
・責任
・データやファイルのバックアップなどインシデントの解決前の予防策
・処理を完了するまでの許容期間、閾値
・エスカレーション手順
・エビデンス保持
重大なインシデント
事業に深刻な中断を与える原因となるインシデントのこと
インパクト
インシデント、問題、変更によるビジネスに与える影響の指標。
緊急度
インシデント、問題、変更が事業に顕著なインパクトを与えるまでの時間の指標
優先度
優先度=インパクト+緊急度
エスカレーション
インシデントをタイミングよく解決できるようにするための仕組み
・機能的エスカレーション
インシデント解決をするために、より専門的なグループに引き渡す
1次サポート サービスデスク
2次、3次サポート インシデントを解決するためのより高度な専門スキル、リソースを所有しているグループ
・階層的エスカレーション
重大なインシデントの場合、上位のITマネージャに情報を提供すること
インシデント管理プロセスの活動
・インシデントの識別
・インシデントの記録
・インシデントの分類
・インシデントの優先度の決定
・初期診断
・インシデントのエスカレーション
・調査と診断
・解決と復旧
・インシデントのクローズ
要求実現
問題管理
アクセス管理
技術管理
アプリケーション管理
IT運用管理
継続的サービス改善
テミングサイクル PDCAサイクル
①ビジョンは何か
事業とITサービスの最終目標を常に意識し、改善の方針にブレがないか確認する
②我々はどこにいるのか?
現状分析し、ビジョン達成に必要な作業を明確にする
③我々はどこを目指すのか?
目標の設定
SMART
Specific
Measurable
Achievable
Relevant 当面の目標にとって適切である
Time-Bound 今取り組むべき内容である
④どのようにして目標を達成するのか?
どのようにプロセス改善を行うかをCSI管理表にまとめる
⑤我々は達成したのか?
改善がちゃんと実施できたのかKPIを用いて計測する
⑥どのようにして推進力を維持するのか?
ベースライン
改善前と改善後の差分を明確にする為に、基準値を設定すること
監視、測定する理由
妥当性確認
意思決定がビジョン通りなっているか確認する
方向付け
意思決定のプロセス妥当性を確認する為
正当化
サービス提供側の正当性を証明する為
介入
変更や是正措置が必要な箇所を特定する為
測定基準
技術測定基準
可用性やパフォーマンスなどITサービスを構成するコンポーネントの測定基準
CPU使用率 メモリ使用量
プロセス測定基準
KPI CSFを測定する
CSF 成功に必要な観点 コスト削減 品質向上など
KPI CSFを達成する為に達成すべき指標
サービス測定基準
技術測定基準とプロセス測定基準を用いてサービスとしての測定基準を算出する
サービス・ライフサイクル全体でのITガバナンス
ガバナンス
不祥事を起こさない組織を作ること
コーポレートガバナンス
外部の法規制やフレームワークに適合すること
SOX法など
ITガバナンス
ISO/IEC38500
7ステップの改善プロセス
①改善に対する戦略の識別
ビジョンの明確化
②測定対象の定義
③データの収集
④データの処理
集めたデータをCSFやKPIが達成できたかわかるように加工する
⑤情報とデータの分析
改善の分析をおこなう
⑥情報の提示、活用
レポートにまとめる
⑦改善の実施


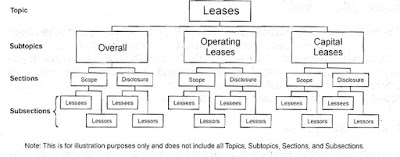



%20De%20uitgebreide%20incidentlevenscyclus.jpg)